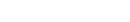2018.02.22 THU XDIVERSITYで目指す「社会の包摂性をテクノロジーで拡張」、その実現に必要なもの ――落合陽一
| text by : | 編集部,落合陽一 |
|---|---|
| photo : | 編集部,masato kato,落合陽一 |

2017年、JST(科学技術振興機構)のCRESTに採択された1つのプロジェクトがある。
“計算機によって多様性を実現する社会に向けた超AI基盤に基づく空間視聴触覚技術の社会実装”、この研究代表者は落合陽一、プロジェクト名はXDIVERSITY(クロスダイバーシティ)
筑波大デジタルネイチャー研究室、ピクシーダストテクノロジーズ株式会社代表、多くのメディア出演や著書など精力的に活動する中で始動したXDIVERSITYが目指すもの、その背景について落合陽一さんに聞きました。
■XDIVERSITYは「人の権利をテクノロジーで拡張する」ことを実現する
――落合さんは大学でご自身のデジタルネイチャー研究室、また、ピクシーダストテクノロジーズというベンチャー企業を進めつつ、このXDIVERSITYはJSTのCRESTの採択事業とし進めています。なぜCRESTだったのでしょうか?
研究できる環境の構築と情報共有を社会全体で取り組まないといけない公益的な側面が大きいからです。それは営利企業の枠組みだけでは難しいので、国や公的機関のサポートの元社会全体の課題として取り組まないといけないと考えました。
例えば義肢装具士会など既存の団体の不断の努力のおかげで今の我々の社会は成り立っていますが、情報技術を用いたテクニカルなイノベーションを共有するには、IT側からもやれることが大きいはずです。
例えば、富士通本多達也さん(xDiversity・主共同研究者)の「Ontenna」のような聴力多様性・難聴の方向けの製品やSonyCSLの遠藤さん(xDiversity・主共同研究者)の「Xiborg」の義足はもちろん単体の事業として利益を出すことは出来ると思います。
しかしながら、こういった多様性補助の分野全体はそもそも、市場が限られるためBtoC事業として大きな売上になるタイプの製品ではないし、ましてや知財の共有や収集したデータの研究のための共有などを考えると、情報技術の側のプロジェクト団体などがないと、発展していかないし、それは海外のIT企業に任せていても我々の社会の問題を解決することができない。
そういった意味で、身体多様性に向き合うプロジェクトやその情報共有のためのコンソーシアム的なものは、課題に対してプロジェクトベースでいくつか進めることができても、それを「社会を支えていく継続的な研究開発活動」として考えた場合、「営利事業としての即座の事業化が難しい」ことが大きな理由です。
非営利で利用できるデータセットや研究の知見の共有が不可欠で、たくさんの事業者の協力もなくてはならない。そうすると公的なバックアップがなければ研究開発がどうしても停滞してしまう。業界団体の政治的やりとりを待っている暇はないし、我々はハードソフトの垣根を超えて協力すべきです。
例えば、営利的な面で考えると、聴覚補助はそもそもニッチな市場に限られますし、補聴器などの値段が未だ高価なのもその現状があるからだと思います。しかし、使い方を考えるともっと非営利のサポートや、長期的な工学的研究とブレークスルーになるような新しい価値基軸でのコミュニティづくりが必要です。
具体例でいえば、 “電車を降りた時にその状況を認識する”とか“個人の趣味に合わせて聞きたい音を変える”といった使い道を考えたとき、地方の駅ではどうするんだとか、その個人の趣味はどこまで対応するんだとか、多様なコンテクストにフィットさせる展開を考えると、単純に営利事業としてその展開を進めていくのは、即座には難しい。
もちろん、高齢化の進行に合わせて、市場としても必要になり、拡大していくことは間違い無いけれど、その時間スパンを考えると、今のうちにコミュニティを作っておくことが重要であるし、必然だと思う。
それは、クラウドファンディングで展開すれば既成のものの運用か枠組みの範囲内で、単発で終わってしまうし、大学の科研費としてやるには規模感が足りない。
そこで非営利・営利問わず適切な大きさのプロジェクトは無いか?と色々検討を重ねた結果、その中で文部科学省系の公的予算である、JST・CRESTがベストだと考えました。その後の展開を含めても、営利企業ではなく、非営利のコミュニティや研究成果共有などがやりやすい。
我々、XDIVERSITYが目指すのは、ダイバーシティ(多様性)に関わるデータセットや公共性の高いフレームワークを考え、展開した先で「社会の包摂性をテクノロジーで拡張するための基盤の構築」・「身体の困難をテクノロジーで解決するというマインドセット」の実現です。
まずは数年間、JSTのプロジェクトとして毎年研究費1億円規模で継続できる枠組みを作る。
その先では年間研究費を5億円くらいに拡張し、そういったプロジェクトに配分し、データの連携を整備していくことで、公営またはNPOといった形で研究を進めつつ、データセットを集め、学会のような非営利的枠組みが理想だと考えています。
何かの身体的困難を抱えた人が、研究者が集う場所に行くと、UIデザイナーがワークショップをして課題や困難を対話の中で発見し、ロボティクスやファブリケーションの研究者がその事例に合わせた問題解決を提案し、コンピュータビジョンやホログラムの研究者がデータセットから知能化の枠組みを構築する。そういった一貫したパイプラインを持った「場」のテストや「実際の困難を知能化によって解決して行くケーススタディ」が不可欠と考えました。

”できないこと”の壁を取り払い、”できること”をより拡張出来たら、本当に個性が活かせる社会になるのではないか。
■XDIVERSITYを“間に合わせるため“に2017年から動く必要があった
――XDIVERSITYは「2017年」のJST CREST採択事業です。このタイミングは何か意図的だったのでしょうか?
タイミングは意識していました。理由は「2020年のオリンピック・パラリンピック」です。
2017年辺りからXDIVERSITYプロジェクトが走り始めないと、パラリンピックに間に合わない。
この時期を逃したら、「身体の多様性」について国民全員レベルで注目する機会や考える機会が無くなる。
身体は人間に同一に与えられてはいない。人によって体型も体質も特徴も違う。センサーもアクチュエータも違うのは自然なことです。それは年齢によっても、生まれによっても、そして人生の様々なイベントによっても、当たり前のように異なってくるものです。
この“身体”というフレームワークに興味をもってもらわなければいけない。
2020年の国民的イベントがあって、そこと僕らが取り組む技術のアプローチが交差すれば、我々が身体多様性に向き合うイメージ、義手義足や車椅子や補聴器や白杖といったものだけでなく、「コンピュータテクノロジーを用いて、人工知能技術やデジタルファブリケーション技術を用いて困難に向き合うこと」について、関心をもってもらえると考えました。
――落合さん以外のXDIVERSITYメンバーが集まった経緯は?
「パラリンピック前に始動する必要がある、じゃあ実際に何をやるか?」となって、最初に菅野さんと本多さんに「こういうプロジェクトいけるかなあ?」とふわっと話しました。
そしたら「いけると思う。非セマンティックだし」って菅野さんの即答と、「やりましょう!!!」という本多さんのエネルギーで、あとは昔からこういうこと一緒にやりたかった遠藤さんにそのあと話してもみんな1秒で「やる」って。皆さんにいつもお世話になっています。もはやバンドですね。
菅野さんは機械学習や認識技術のプロ、特にカメラや視線を扱わせたら若手のトップ研究者です。また、本多さんはプログラミングとデザインとユーザーとの対話による問題発見が出来て、例えば「聴覚障がい」にフォーカスしてどうアプローチするか?の枠組み自体をデザインできる。
遠藤さんは根っからのテクノロジストで、テクノロジーを用いて課題解決に向き合うお手本のような人、課題解決のための技術要件にフォーカスしてゴールまで走りきるということを何度もやってきている。ここを繋いでコミュニケーションが成立したら、発展性が物凄く高いなと思いました。
問題にフォーカスする人、枠組みをデザインできる人、研究によるアカデミックなアプローチが出来る人が揃い、タイミングがピッタリだったというのは大きいです。その点僕のラボは、波動と物質の出会うところをCGをベースにしたコンピュータサイエンスで解決して行くという何でも屋なのでいい潤滑剤というか、接着剤になるかなと思いました。
こういうテーマは我々の社会の成熟度や価値基軸の変化に応じて、研究開発をずっと続けるべきものだし、議論は止めてはいけない。文化を形成しないといけない。その面では営利目的で継続するよりも大学など非営利なものと相性がいい。この点もJSTの方向性にフィットしました。

■社会的な困難を技術によって解決することが使命なら、企業も参加可能な仕組みが必要
――身体の多様性、技術による補完をテーマにする事業やサービスが増えていますがどう思いますか?
それXDIVERSITYになぜ本多さんや遠藤さんがいるのか?の重要なポイントです。
本多さんは富士通の人、遠藤さんはSonyCSLの人。ここに凄く意味がある。アカデミックだけでも企業体だけでもおそらくこの問題への継続的アプローチは成立しないのです。
彼らは企業に属しながら、企業の枠組みを超えた活動をしています。
恐らく「市場が狭いから無理やり新規性を出す」「事業としてのやりくり」をすることに囚われていないはず。
僕自身がこのプロジェクト自体を営利事業としてやらないと決めたのも、1企業単位でやりきれるサイズ感じゃないと思ったからです。事業展開する中で競争相手と戦う、無理やり新規性を出すために動く。市場原理を働かせることはある意味正しいけど、どこか公共の福祉に反する気がしています。
――事業としての競争より、社会にあるべきものを提供するための座組みが必要
僕の理想論で言えば、社会共同体として富士通やソニーに限らずあらゆる企業が本多さんや遠藤さんのような人を迎え入れて、その人たちが意思決定できる権限を与えるべきだと思います。
「べき論」は好きでは無いけど、僕はこの高齢化と人口減少が進むフェーズの日本においては、それが社会正義だと認識している。
一方、本多さんや遠藤さんは「そういうポジション」だからこそ見えているものがある。
企業の枠組みを超えて活動するときの不自由さ、リアルな経験や知見はおそらく社会全体にとって共有すべきだし、彼らの現場で向かい合ってる努力は非常に価値あるものです。
この「リアルさ」が僕の理想論を実際に動かす時に重要だなと。
――企業側の論理や事情も踏まえて巻き込む必要がありますよね
むしろXDIVERSITYのような枠組みに大手企業が参加することもできるはず。
例えば大抵の企業は富士通が本多さんを雇うくらいの金額をCSRとして出すことができます。
そのお金を出資金額として研究者を雇う、そこで出た研究成果はパテントプールして貯めておき、参加企業がデータと共に利用できる。XDIVERSITYの中では常に企業や研究者が集まって活発に議論している。そして、そこに問題解決してほしい人が来る、それを集団で解決するようなチーム編成とワークショップなどの課題発見の枠組みがあること。
成熟社会には、そういうサステナブル(持続性のある)な研究開発・コミュニティデザインの枠組みがありえるなって。
「社会的な困難を技術によって解決し、市場において活発な経済活動を進めることが、技術企業の使命」という社会正義があるなら、XDIVERSITYに全ての企業がコミットメントしてお金を出し、そのリターンとしてXDIVERSITYのデータベースとソフトウェアライセンスを使えるような、企業側にメリットのある仕組みも必要。その枠組みを公益性に関わるリソース管理を行うか、または非中央集権化して、このあたりをちゃんと整理していくつもりです。

■まずは「聴覚多様性」と「人の移動を知能化」に取り組む
――そのサステナブルな枠組みを実現するために「まずはXDIVERSITYでここまでやらないと」と意識しているものはありますか?
克服可能そうなもので2つくらい進めることですね。その一つが「聴覚多様性」
近視がメガネによって克服されたように、聴覚も文字起こしとリズムパターン伝達で近い将来克服できるのでは?という仮説があります。
視覚代替には画像認識と読み上げが必要だけど、聴覚は「言語認識」の枠組みの中で代替できる。普段僕らは耳で誤変換したものを聞き流せるから、言語コミュニケーションが成立する。
となると、聴覚障がいの方に「目で適当に読み飛ばす」能力が身につけば、あとは発話タイミングと意味の取得だけになる。それを網膜投影やアイトラッキング、「自分に関係のある音だけ認知する」といった音源の知能化で実現したら克服可能だなと。
――1つ目が聴覚障がいで、2つ目はなんでしょうか?
あとはロボティクスです。「人の移動」を知能化するためにセンサーを賢くする。
この聴覚障がいと移動の知能化は最低限XDIVERSITYプロジェクトの最初の2年で成果を挙げたいと考えています。
ここまで進めば、その先でどうやって社会の中で訴求するか、上にあげたような枠組みを何度回せるか、エンタメ領域とコラボして発信するか?データセットをどう公開すべきか?といった「一通りの手順」が知見として溜まる。
すると「聴覚の次は視覚」「車いす(下肢)の次は義手」となった時、プロジェクトを走らせるための骨格やデータをリリースするホスト、賛同者や実際の困難を持つ方とのコミュニケーションの仕方がわかってくると思います。ITを用いたその解決や貢献を行って行く必要がある。
――ウェブサイト上でも、実際に障がいを持つ方や支援団体への協力も呼びかけていますよね。
すでに幾つかの支援学校や老人ホームからお声がけ頂いて一緒に現場レベルで動き始めています。ポジティブな反応をもらうこともあれば、「この機能いらない」とか細かい点もわかってきて、こういう動き出しが出来たのは大きい。
その反応を得るためには、1個持っていってもダメで、10個持っていってその中で本当に支持される1~3つのポイントを知る必要がある。だから考究や継続的な研究が必要だなと。

多くの連絡をもらい、少人数で対応しているため連絡できていない状況らしい。
「ちゃんと全てに目を通しているし、ちゃんとリストに分けています!(落合さん談)」
■データを集めただけで社会は変わらない。研究に活かし続けることが重要
――もう一つ、企業や団体にデータ提供を呼び掛けています。ここでいう「データ」とは?
例えば車椅子スポーツの団体が、「過去20年分の選手の身体・欠損部位」の情報を持っていたら、そのデータをもとにとある運動に最適なその人用の車椅子の設計ができるかもしれない。こういった例とデータのサンプルはニーズの仮説を議論する際に相当意味のあるものだと思います。
そこまで直接的でなくても、「聴覚を視覚で補完」のような欠損した能力を何かで補う場合、データをクロスモーダルすることで役に立つことはある。例えばコンビニのおにぎりのラベル画像とか、地下鉄の標識とか。
――身体・医療分野のデータに限らないってことですか
以前、視覚に困難がある方の実際に困っている例として、「ラベルが見えないから、おにぎりの具は勘で選んでいる」っていう話を本多さんから聞いたんです。
それデータとスマホがあれば解決するじゃないですか、僕らにコンビニのおにぎりラベルデータ提供してもらえたら、視覚困難者向けに「ラベルを読み上げる」くらい余裕で出来る。
先日、自分のピクシーダストテクノロジーズの法人がメルカリと共同研究(mercari R4D)始めたのも、そういうことを見据えて考えています。データで多様性を包摂するとはまさにそういうこと。
もしヤフオク、アマゾン、楽天、コンビニまで協力してもらえれば世の中で流通する製品画像の大半が手に入るかもしれません。メルカリにおにぎりは出品されていないかもしれないけど、どこかの企業の中には、大抵の商品データがラベル付きで整理されていますから。
これを非営利のどこにも属さない立場で個別に適切な秘密保持契約とセキュアな認識システムを構築できれば成立します。でもデータを集めただけじゃ社会は変わらない。そのデータを使って研究を進めることで収入を得る研究者が数10人いるような非営利団体があれば、より価値が高いはず。
もちろん、筑波技術大学など、専門の教育機関もあり日々努力が行われていますが、アカデミックとビジネス、社会実装と文化構築の適度なミックスがないと社会のアップデートをすることは難しい。
この「データ」と「研究」が両輪でうまく回るようにXDIVERSITYが最初の2年で検証し、その後3年は徐々に拡大する、そういう非営利団体が作れたら凄く価値が高いなと

“多様性の問題”をやると決断するかどうかだと思っていた」
■「いまこそテクノロジーの力、見せたれよ!」と思った。
――最近落合さんは「計算機多様性」という言葉よく用いていて、多様性への関心が高まった結果のXDIVERSITYなのかな、と思っていたのですが
僕は昔から「ダイバーシティめちゃめちゃ肯定派」な考えを持っています。
世界は本質的に多様、ある道徳観念は成立する場所としない場所がある。べき論はあまり好きでないし、文化がもたらす倫理や価値観は多様でいいと思っているから、何かの考え方を頭ごなしに否定することは好きではない。
ただ今回の取り組みに対して、「XDIVERSITYプロジェクトをやる!」となったのは、自分の子供が口唇口蓋裂で生まれてきたことが大きいかなと思ってます
――そのお話、実は聞こうかどうしようか迷っていたんですよ。
普段あまり書かないけど、ちゃんとメディアで一言くらい触れてもいいかなって。
僕は、自分の子供が口唇口蓋裂という先天的な身体多様性をもって生まれてきたことは別に嫌ではなくて、むしろ「いまこそテクノロジーの力を見せたれよ」って思ったんですよね。
生後2日目に歯医者の方が口の型をとって、「ミルクが飲めるように」って顎に装着する器具を一瞬で作ったことに衝撃を受けて。「すげえ、デジファブ(デジタルファブリケーション)だ!」って。
その後も言語聴覚士さんが言葉のトレーニングをする話とか、要は口唇口蓋裂って200人か500人に一人、1億人換算で20-50万人くらいいるので、器具とか矯正に必要な技術・産業・治療のフレームワークが成立していたわけです。
ここでは論文もたくさん書かれていて、「そうか数十万人規模ならシステムが成立するのか」って感動すると同時に、聴覚や視覚、四肢欠損など個別の身体困難の「単体」では成立させづらいことも気が付いたんです。
――身近な話題化すると同時に、個別で解決が難しい現実も気づいた。
じゃあどうすれば解決できるか?を考えたら、医学領域に限らずコンピューターサイエンスだと。
身体の多様性って一言でいっても個人差がある、個人の状況にあわせて最適化したり、多くの場合ファブリケーションが必要になる。また、量子化されたデータの世界では、物理的制約を飛び越えて知見やソースコードが共有可能です。
医療は治療や手術で器質的に治そうというアプローチが可能ですよね。外科手術や遺伝子治療、医療保育とか。逆に、そこをサポートする形で、僕らは「物質的でそれでいて低侵襲なアプローチ」で何かが出来ると思ったんです。
聴覚や視覚を補完するために周波数を変えたり、網膜投影したり、振動を最適に伝達したり、四肢をサポートしたり、外界を認識したり。
僕らは幸いなことに、今、営利を目指していないし、情報技術を扱ってる限り、ほかの団体と領域が異なっている。おかげで市場で競合するような人もいないし、競合するくらいなら「非営利なんでデータ共有しますよ」とか、そういうグッドな関係性を各団体と築いていきたいなと考えています。
つまり、色々な団体が足並みをそろえて行くための潤滑油や接着剤としてデータや人工知能の力を使えればいいなと思うんです。決められた公的予算をとりあうとゼロサムゲームだけど、市場と社会とうまくコミュニケーションしていけば、今の日本の社会要請を考えてもこの領域は成長しうる領域だからね。
――ありがとうございました。

インタビュー:波多野智也(アスタミューゼ株式会社)
- X DIVERSITY [クロス・ダイバーシティ]
- JST CREST|【落合陽一】計算機によって多様性を実現する社会に向けた超AI基盤に基づく空間視聴触覚技術の社会実装
- 落合陽一 デジタルネイチャー研究室
- Ontenna - 髪の毛で音を感じる新しいユーザインタフェース
- Xiborg | Delight of Locomotion for All People
- 業界特化型の転職サイト | ベンチャー・スタートアップ転職ナビ
-
 Interview2017.07.06 THU 人間の脳は平均7時間寝るのが最適な作り。短い睡眠時間でごまかす方法はありません – 筑波大…ナルコレプシー(睡眠障害)の原因に繋がる物質「オレキシン」を1998年に発見、その後も睡眠研究の世界…
Interview2017.07.06 THU 人間の脳は平均7時間寝るのが最適な作り。短い睡眠時間でごまかす方法はありません – 筑波大…ナルコレプシー(睡眠障害)の原因に繋がる物質「オレキシン」を1998年に発見、その後も睡眠研究の世界… -
 Column2020.07.31 FRI 今からでも遅くない!各産業のゲームチェンジャーとなりえる量子技術の導入・R&D投…第2回 量子コンピュータ・量子アニーリング・量子ソフトウェア・量子AI最新萌芽技術のプレイヤー <目…
Column2020.07.31 FRI 今からでも遅くない!各産業のゲームチェンジャーとなりえる量子技術の導入・R&D投…第2回 量子コンピュータ・量子アニーリング・量子ソフトウェア・量子AI最新萌芽技術のプレイヤー <目… -
 Interview2019.10.01 TUE 水を、未来を解き明かす。——株式会社地圏環境テクノロジー 田原康博2018年、西日本豪雨で甚大な被害を受けたことは記憶に新しいです。雨による地滑りがいつ起こるか、どこ…
Interview2019.10.01 TUE 水を、未来を解き明かす。——株式会社地圏環境テクノロジー 田原康博2018年、西日本豪雨で甚大な被害を受けたことは記憶に新しいです。雨による地滑りがいつ起こるか、どこ… -
 Interview2018.04.23 MON 「研究の民主化」組織や分野の壁を越え、新しいものを生みだす未来の研究者 ――Co-LABO…総合化学メーカーで材料系のR&Dや新規事業立ち上げに従事しながら「視野が狭くならないように…
Interview2018.04.23 MON 「研究の民主化」組織や分野の壁を越え、新しいものを生みだす未来の研究者 ――Co-LABO…総合化学メーカーで材料系のR&Dや新規事業立ち上げに従事しながら「視野が狭くならないように…